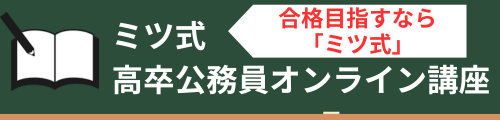作文って何書けばいいの?初めてでもわかる書き方のコツと練習法
「作文があるって聞いたけど…何書けばいいか全然分からない…」
「テーマが難しそうで、書き始めることすらできない…」
そんな悩みを、私はこれまでに数えきれないほど聞いてきました。
公務員試験において、作文(小論文)は重要な評価項目のひとつです。
ですが、多くの受験生が「筆記や面接の対策に追われて、作文は後回し…」という状況に陥ってしまいます。
そして気づいた時には──
・「作文に“足きり”があったなんて知らなかった…」
・「筆記ができていたのに、作文で落ちてしまった…」
そんな声が毎年のように聞こえてくるのが現実です。
でも、安心してください。
作文には、“守るべき型” があります。
その型と、テーマに対する“自分なりの意見”をセットにすれば、誰でもしっかりと書けるようになります。
この記事では、
✅ 作文で落とされる人の共通点
✅ 書き方の基本構成と、考え方のコツ
✅ 自宅でできる簡単な練習法
を、わかりやすく解説していきます。
「作文が苦手…」「そもそも何を書けばいいのか分からない…」
そんなあなたでも、“伝わる作文”を書けるようになる一歩目をこの記事で踏み出せますよ!
① 作文で“落ちる”人の共通点とは?
まず最初に知っておいてほしいのは、
作文で落ちる人にはいくつか共通点があるということです。
📌 こんな特徴に当てはまっていませんか?
- テーマからズレた内容を書いてしまう
- 結論があいまい or 言いたいことが分からない
- 原稿用紙のマスの使い方にミスがある
- 文字数が足りない(または極端にオーバー)
- 誤字・脱字・文法の乱れが多い
つまり、「内容以前に、基本的なルールが守られていない」ケースが非常に多いんです。
✅ ポイント: 作文は“思いつきを書く場”ではなく、“伝わるように書く場”です!
だからこそ、最初にしっかりと「型」を身につけておくことが大事なんですね。
② まずは「型」を覚えよう!作文の基本構成
作文が苦手な人ほど、「何を書けばいいか分からない…」となりがち。
でも、型さえ覚えてしまえば、 どんなテーマでも“伝わる文章”に仕上げることができるんです!
📌 作文の基本型(黄金パターン)
① 結論(私は〜だと思う)
② 理由(なぜなら〜だからだ)
③ 具体例(例えば〜という経験がある)
④ まとめ(だから私は〜と考える)
この4つのパートを使えば、「主張+根拠+経験+まとめ」の形が自然に作れます!
→ 実際にこの型で書くと、こんな感じになります👇
📝例)テーマ:「働くことの意義」
私は、働くことの意義は「人の役に立つこと」だと思います。
なぜなら、人に感謝されることが自分のやりがいにつながるからです。
私は以前、地域の清掃ボランティアに参加したことがあります。通学路を掃除した後、近所の方から「ありがとう」と声をかけてもらったことがとても嬉しく、達成感を感じました。
だから私は、働くことで誰かに喜んでもらえることが、自分の原動力になると考えています。
どうでしょう?
難しい表現は一切なし。それでも「伝わる作文」になっているはずです✨
③ よく出るテーマはこれ!頻出作文テーマリスト
作文のテーマはバラバラに見えても、実は“出やすい傾向”があります👇
🔹 よく出る作文テーマ
- 公務員としての心構え
- 働くことの意味
- 少子化・高齢化などの社会問題
- 最近のニュース(災害・経済など)
- あなたが力を入れたこと(部活・ボランティア等)
🟡 ポイント:時事や社会的なテーマに“自分の意見”をしっかりのせられるかがカギです!
④ 自宅でできる!作文練習のすすめ方
いきなり書き始めようとすると、手が止まってしまうこともあります。
そこでおすすめなのが、以下の3ステップ👇
🔸 ステップ①:「テーマ×型」で下書きする
→ 例:「少子化」をテーマに、型(結論→理由→具体例→まとめ)で整理
🔸 ステップ②:書いた内容を“音読”してみる
→ 自分で読んでみて、スムーズに伝わるか確認!
🔸 ステップ③:先生や保護者に見てもらう
→ 客観的に見てもらうと「分かりにくさ」が見つかります
🟡 1週間に1テーマだけでもいいので、継続していけば“作文筋”がついていきます!
⑤ 作文の“足きり”に注意!
最後に、絶対に押さえておいてほしいのが「足きり」の存在です。
特に「税務職員」試験では、
作文は「合否の判定のみ」行うとなっています。つまり、作文が「否」となれば、 面接試験が高得点、筆記試験が高得点でも不合格になることがあります。
また、「裁判所事務官(高卒者区分)」では、1次試験で作文試験は実施されるものの…
「作文試験の評定結果は、第1次試験の合格者決定には反映させず、最終合格者の決定の際に、他の試験種目の成績と総合します」 となっています。
他にも、東京消防Ⅲ類では、「教養試験の成績が一定点に達しない場合は、作文試験の採点及び資格・経歴の評定を行いません」となっています。
💡ちなみに、令和7年度の試験から、東京消防Ⅲ類は作文が「600字以上800字程度を1時間で実施」に変更となりました。
令和6年度までは、「800字以上1200字程度、1時間30分」で実施されていたため大きな変更点です。ご注意ください。
🟡 つまり…作文は足切りもあるし、教養試験をクリアした人たちのみ採点されたり、最終合格の決定の際に用いられてたりする超重要分野なんです。
作文=受験の合否を左右する“重要科目”なんです。
だからこそ、早めに練習を始めておけば安心です!
【まとめ】作文は“技術”です。今から始めれば誰でも書ける!
作文に必要なのは、「文才」でも「センス」でもありません。
✅ 伝える“型”を覚える
✅ 自分の意見を整理する
✅ それを“自分の言葉”で書く
この3つができれば、しっかりと相手に伝わる作文が書けるようになります。
「作文が苦手…」と感じている今こそが、始めるチャンス。
ぜひこの記事を参考に、“伝わる文章”を書けるように準備していきましょう✍️✨
📣【公式LINEで無料特典プレゼント中!】
ミツ式 高卒公務員オンライン講座では、
公務員試験に挑戦する高校生や既卒生、保護者の方に向けて
「勉強法・試験制度・面接対策」など、役立つ情報をLINEでお届けしています!
今ならLINE登録で👇
✅ 公務員試験のしくみや対策ポイントがわかるPDF
✅ よくある悩みを解決する限定動画プレゼント
など、登録者限定の特典を配信中です!
今すぐ登録して、効率よく合格を目指す一歩を踏み出しましょう✨
こちらからカンタン登録!(無料特典もすぐ届きます)
👉【LINE登録はこちら】https://kno2ezbf.autosns.app/line