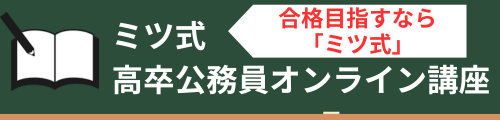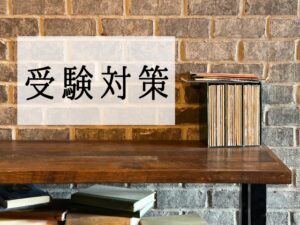日程が重なるって本当?高卒公務員試験のスケジュールと併願戦略
「○○市と△△市、どっちも受けたいけど、試験日って被らないのかな…?」
「公務員試験って、よく試験日程が重なるから受験できる数が少ないって聞くけど…併願はできそうにないのかな?」
こんな不安を感じている高校生や保護者の方も多いのではないでしょうか。
実は、高卒程度で受験できる公務員試験の多くは、**「9月〜10月に集中して実施」**されるため、複数の試験が同じ日に行われる=併願できないというケースは、確かにあります。
でも、逆に言えば「試験日程や試験制度の特徴」や「併願のパターン」をあらかじめ理解しておけば、実は無理のないスケジュールで併願を増やして、合格チャンスをしっかり増やすことができます!
実際に私の教え子は、年間で40(!)程の公務員試験を受験していました。
この記事では、
- 高卒公務員試験のスケジュールと試験制度の特徴
- 併願が難しい組み合わせ
- 効率よく合格を目指すための戦略
などを、わかりやすく解説していきます。
公務員試験の“併願戦略”をしっかり立てたい方には、きっと参考になるはずです!
「どう併願すればいいのか分からない…」
「可能性広げるためにも、とりあえずたくさん受けてみたいんだけど…」
そんな悩みや疑問を持っている方にとって、後悔しない受験スケジュールの立て方がわかる記事になっていますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね!
➀高卒公務員試験は「秋」に集中している
高卒程度で受験できる公務員試験の多くは、毎年「9月〜10月」に一次試験(筆記)が集中しています。
特に高校3年生である現役生が受験できるような公務員試験(詳しくは前回の記事をご覧ください)は、ほぼこの時期にまとまって実施されるため、短い期間にいくつもの受験をこなす必要があるというのが現実です。また、大半の公務員試験(一次試験)は、日曜日に実施されます。ですので、9月は、ほぼ毎週日曜日は公務員試験が実施されると思ってもらえればいいかなと思います。
②実は多くの試験が“日程バッティング”している!
具体的には、こんなパターンで重なってきます👇
・国家一般職と税務職員(例年、9月の1週目の日曜日に実施)
・皇宮護衛官と入国警備官と海上保安学校学生と航空保安大学校学生(例年、9月4週目の日曜日に実施)
・気象大学校学生と海上保安大学校学生(例年、10月4週目の土曜日と日曜日⇒この2つの試験は1次試験を2日間で実施します)
・裁判所事務官と東京都3類と東京都特別区(例年、9月2週目の日曜日。)
・県庁と政令市(例年、9月4週目の日曜日。ですから、上記した皇宮護衛官などとも被っています)
・各市町村(規模が似通った近隣市町村は日程が同じになることが多いです)
この他にも、例えば警察官試験は、統一されているわけではないですが近隣県の試験日は重なることが多いです。四国各県の警察官B区分(高卒)の試験は10月3週目日曜日実施で重なることが多いですし、九州では、福岡県警と大分県警と鹿児島県警が9月3週目の日曜日で重なりますが、他の佐賀県警、長崎県警、熊本県警、沖縄県警は10月3週目日曜日の実施になっています。
このようなこともあり、「受けたい自治体が重なってて両方受験はムリだった…」という声が毎年のように出てきます。
※上記の日程はあくまで参考です。試験日程は年度によって変更となることもありますので、受験の際は必ずご自身で日程は確認しましょう。
③併願パターンの具体例
✅ 併願しやすい組み合わせ(一次試験)
【事務系職種でよくある併願パターン】
・9月1週目:国家一般職 or 税務職員
・9月2週目:裁判所事務官 or 東京都庁 or 特別区
・9月3週目:刑務官(筆記試験の練習等の位置付けで)
・9月4週目:県庁 or 政令市
・10月 :市町村職員試験
【公安系職種でよくある併願パターン】
・9月1週目:東京消防3類
・9月3週目:警察官 or 刑務官
・9月4週目:政令市消防吏員 or 海上保安学校 or 入国警備官 or 皇宮護衛官
・10月3週目:市町村消防吏員 or 警察官
※実際に「受験案内」で試験日を確認するのが一番確実です!
④併願受験を増やす方法
✅ 併願の幅を広げるカギは「テストセンター方式」!
実は近年、一部の地方公務員試験や民間企業の試験で導入が進んでいる「テストセンター方式(SPI3・SCOAなど)」が、高卒公務員受験における“併願の壁”を取り払う存在になってきています。
従来の公務員試験では、すべての受験者が同じ会場・同じ時間に集まって試験を受ける集合形式が一般的でした。
しかし、テストセンター方式では、
・決められた期間内に
・自分で受験日時と会場(テストセンター)を予約し
・予約日時にテストセンターへ行き、指定されたパソコン環境で受験する
というスタイルのため、**今まで試験日程が“被っていた地域でも併願が可能になる”という大きなメリットがあるんです!
🔍 テストセンター方式の導入自治体は拡大傾向!
コロナ化以降、高卒区分でもテストセンター方式を導入する自治体がじわじわと増加中です。
(多分、コロナ化において各自治体が集合形式で試験を実施し、そこでクラスターでも発生しようものなら…ということで導入が進んだのでは?と私自身は考えております笑)
・SPI3やSCOAを活用する市町村
・書類選考+テストセンターで筆記通過を判定する自治体
など、従来の「紙+一斉試験」とは異なる形式が取り入れられつつあります。
📌 併願チャンスを逃さないために
1. 志望先の試験方式を確認することが最重要!
→ 受験案内に「テストセンター方式」と書かれていたら要チェック!
2. 試験期間と予約枠の有無も確認を
→ テストセンターは先着順の予約が多いため、スピードも大事!
3. 「SPI3」「SCOA」といった試験の傾向を早めに対策
→ CBT形式(PC画面での出題)に慣れておくと安心!
④ 併願戦略の立て方(失敗しないスケジュール管理)
1. まず“第一志望”を決める
→ これが決まらないと他の予定が組めません。
2. 過去の試験日程を調べる(例年ほぼ同じ)
→ 「〇〇市 2024 公務員試験日程」などで検索すると出てきます。
※但し、SPIやSCOA試験が突然新年度から導入される場合もあるのでその点は要注意!
※必ずあなたが受験する年度の試験日程も後日調べること!
※ここでお伝えしたいのは、併願するために過去の日程の傾向を知るということです。
3. 申し込み締切にも注意!
→ 「受けられると思ってたのに、締切が既に終わっていた…」というミスが出ないよう要注意!
【まとめ】過去の試験スケジュールを調べ、そこにテストセンター方式をうまく入れ込めば、受験の幅が広がる!
いかがでしたでしょうか?
高卒で受けられる公務員試験は意外と数が多く、併願も可能なことをお判りいただけたでしょうか?
しかし…「受けたい試験が同じ日に重なるリスク」があるため、戦略的なスケジュール管理が欠かせません。
自分の志望に優先順位をつけて、
「本当に受けられる試験」「スケジュール的にムリな試験」をしっかり見極めておくことで、無駄な準備や混乱を減らし、確実に合格への道を歩んでいけます。
そして、テストセンター方式は「日程がかぶって併願できない…」という悩みを減らし、より多くの自治体にチャレンジできる可能性を広げてくれる存在です。
ですから、
「どうしても複数の自治体を受けたい!」
「数撃ちゃ当たる、ではないけど、多くの試験を受けて少しでも合格の可能性を高めたい!」
という方は、SPIやSCOAで試験を実施している自治体・スケジュールを早めにチェックして、併願可能なプランを立てていくことが、合格への近道となります。
このブログを読んだ方が、「なんとなく受ける」ではなく、
計画的に併願して合格のチャンスを最大化できるように願っています✨
📣【公式LINEで無料特典プレゼント中!】
ミツ式 高卒公務員オンライン講座では、
公務員試験に挑戦する高校生や既卒生、保護者の方に向けて
「勉強法・試験制度・面接対策」など、役立つ情報をLINEでお届けしています!
今ならLINE登録で👇
✅ 公務員試験のしくみや対策ポイントがわかるPDF
✅ よくある悩みを解決する限定動画プレゼント
など、登録者限定の特典を配信中です!
今すぐ登録して、効率よく合格を目指す一歩を踏み出しましょう✨
こちらからカンタン登録!(無料特典もすぐ届きます)
👉【LINE登録はこちら】https://kno2ezbf.autosns.app/line