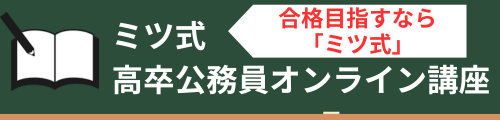【公務員試験の作文】「協調性」をテーマにした時の書き方と例文解説
「“協調性”ってテーマで書けって言われても、何を書けばいいのか分からない…」
「そもそも、自分に協調性があるかどうかも分からない…」
──そんな悩みを持つ受験生、多いと思います。
でも大丈夫!
協調性は特別なリーダー経験がなくても、**日常の中で誰もが持っている“強み”**なんです。
この記事では、
✅ 「協調性」の作文で評価されるポイント
✅ 書きやすい構成テンプレート
✅ そのまま使える!例文と解説
をわかりやすく紹介します!
▶▶【無料特典】「公務員試験スタートガイド」を配布中!ミツ先生の公式LINEはこちら!
【1】作文テーマ「協調性」で見られているポイントとは?
公務員試験における作文で「協調性」がテーマになった場合、面接官(採点官)は次のような点を見ています👇
🟢 チェックポイント
- 困難な場面で、周囲とどう協力したか
- 自分の立場だけでなく、相手の気持ちを考えた行動ができているか
- 経験を通じてどんな学びを得ているか
- その学びを“公務員としてどう活かすか”につなげているか
📌ポイントは、「ただ仲良くやった話」ではなく、
👉 “違い”や“ぶつかり”をどう乗り越えたか を書くこと!
📖関連記事:「作文試験って何が見られるの?高卒公務員試験のポイント解説」
【2】書きやすい構成テンプレート
書くときに迷わないように、以下の「4段構成」で考えるのがおすすめです👇
🔸構成テンプレート
① 序論:「協調性は大切だ」と思ったきっかけ
② 本論①:実際のエピソード(困難や課題)
③ 本論②:そのときどう考え、どう行動したか
④ 結論:得た学びと、それをどう公務員として活かすか
【3】実際に使える!作文例文と解説
✍️例文:テーマ「協調性」
私は高校時代、文化祭実行委員としてクラス企画の運営に関わった経験があります。
意見がぶつかり、クラス内がバラバラになりかけた時期がありましたが、その時の経験を通じて、協調性の大切さを実感しました。
文化祭の準備では、限られた時間の中で出し物や装飾、役割分担を決めなければならず、最初の話し合いでは意見がまとまりませんでした。
「もっと派手なことがしたい」「地味でもいいから確実にやろう」など、意見が食い違い、雰囲気も悪くなってしまいました。
私はそこで、自分の意見を通すのではなく、まず全員の意見を一度紙に書き出して整理することを提案しました。
また、全員で共通して「やりたいこと」「避けたいこと」を共有する場を設け、最終的には“参加型の縁日スタイル”という企画にまとまりました。
全員が自分の役割に納得し、協力し合って完成させた当日は、大きな達成感を得ることができました。
この経験を通じて私は、**協調性とは「相手の話を聞き、お互いにとって最善の道を探す力」**だと学びました。
公務員として地域の人々と関わる際にも、相手の立場に立って考えること、異なる意見をまとめる姿勢を大切にしていきたいです。
🔍ワンポイント解説
✅ リアルなエピソードを選ぶ(文化祭・委員会・部活など)
✅ 困難な場面をしっかり描くと、協調性がより際立つ
✅ 最後は必ず「公務員としてどう活かすか」で締める!
\\公式LINE登録者に公務員試験に役立つ特典を無料進呈中!詳しくはこちらから!//
【4】作文に自信がない人へ|3つの対策ポイント
① 書く前に“箇条書きメモ”を作る
👉 自分の経験・そこで考えたこと・学んだことを書き出すだけでも整理できる!
② 「結論→理由→体験談→再結論」の流れで話してみる
👉 文章を書くのが苦手な人は、この順序で口に出してみるとスムーズ!
③ 他人と比べず、“自分なりの努力”を言語化する
👉 大事なのは「派手な経験」よりも「どう考えて行動したか」です!
【まとめ】協調性は“誰でも持っている”公務員としての強み!
✅ 協調性の作文では、“ぶつかり”や“違い”をどう乗り越えたかがカギ
✅ 経験→学び→公務員への活かし方 の流れで構成を組もう
✅ 特別な実績がなくても、自分の姿勢を伝えれば大丈夫!
📩「筆記試験が不安…」「面接も心配…」という方は、
✅【LINE登録で無料特典プレゼント中!】
- 「模試で点が伸びない理由」動画
- 「面接が苦手な人向けの攻略法」動画
👇 今すぐこちらから登録して、受験準備を加速しよう!